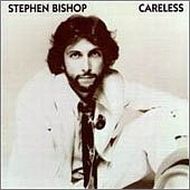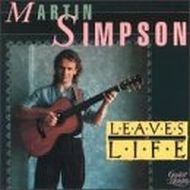●Back Street Crawler: Second Street

Paul Kossoff (g)
John ‘Rabbit’ Bundrik (key, vo)
Tony Braunagel (ds, vo)
Terry Wislon (b, g)
Terry Wilson Slesser (vo)
ブリティッシュ・ロックを代表するバンドといえば、レッド・ツェッペリンやザ・フーなど、枚挙に暇が無いが、派手さにはかけるものの、どうしても気になっていたのがフリーだった。ヴォーカルのポール・ロジャース(最近ではクィーンのヴォーカルとして脚光を浴びていたが)を中心としたこのグループは、シンプルなスタイルながら、ズンズンと心に響いてくる演奏をしていた。
フリーのメンバーでひときわ輝いていたのが、ギターのポール・コゾフ。ギブソンのレスポールを使い、ひたすら泣きまくるフレーズには、単なる哀愁を越えて、鬼気迫るものすら感じさせられた。コゾフ独特の深いビブラートは、ちょっと聞いただけでも彼だとわかるトレードマークようなものだ。
「All Right Now」が大ヒットすると、フリーは一気にトップ・グループへと駆け登っていく。その一方、メンバー間の軋轢がだんだんと大きくなり、ついにはバンドを解散、それぞれが別のグループを編成して活動を開始する。しかし、いずれもあまりパッとした成果を挙げられなかったこともあり、わずか一年余りでオリジナルメンバー4人でフリーを再結成することになる。
以前から、コカイン依存が強かったポール・コゾフは、再結成後、さらにドラッグに浸るようになり、だんだんと演奏活動も満足におこなえないようになっていく。この状況に嫌気をさしたベースのアンディ・フレイザーがバンドを脱退。さらに、ツアーでもコゾフはギターを弾けないようなことが続く。結局、ツアー途中に新しいギタリストを加えて演奏を続けて急場をしのいだりするが、バンドとして問題は山積みとなり、再度解散という結末を迎えてしまう。
フリーの2度目の解散後、奇跡的に状態が回復したコゾフは新たなメンバーとともにソロアルバムをリリースする。このアルバムがなかなかの好評だったことに気をよくしたコゾフは、『バック・ストリート・クローラー』というアルバムのタイトルをそのままバンド名として、自身のバンドを正式に結成して演奏活動をしていくわけである。
しかし、コゾフのドラッグ依存症はひどくなる一方で、バンドとしてわずか2枚のアルバムをリリースした後、移動中の飛行機内で、ドラッグ多用が原因となる心臓発作のため、わずか25歳の若さでこの世を去ってしまう。
このアルバムは、バック・ストリート・クローラー名義の2枚目。コゾフが死んだ直後のリリースだったためか、邦題は『2番街の悲劇』というものだった。ジャケット裏に小さく、「KOSS(コゾフの愛称)に捧ぐ」とあるのが痛ましい。1枚目に比べると、コゾフのギターは少し控えめになっているが、オリジナル期のフリーの音楽性をストレートに受け継いでいる本作は、佳作といってよい出来だ。
クレジットを詳細に見ると、ポール・コゾフ(リードギター)となっているのに気付く。つまり、リード以外はベーシストでもあるテリー・ウィルソンがギターを弾いているのである。おそらく、すべてのギターパートを弾くことができるほどには、コゾフのコンディションはよくなかったのであろう。1枚目では、ギターを弾きまくっていたのとは好対照だ。
改めて、じっくりと聴きなおしてみると、アコースティック・ギターの使い方がうまいのに感心する。ツェッペリンなどにも感じるのだが、ブリティッシュのトラッド・フォークの演奏スタイルが刷り込まれているがごとく、ダークでウェットなブリティッシュ独特の雰囲気のアコースティック・ギターがなんとも言えず良い。同じロックでも、バーズなどのアメリカン・ウエストコースト・サウンドでは、とても粋なサウンドに仕上がっているが、ブリティッシュ・ロックとなると、やはりどこかにブルースの香りが残る、泥臭さがある。そして、それが魅力でもある。
ジョン・メイオールのブルース・ブレイカーズに在籍していたエリック・クラプトンの演奏を聴いて、ロック・ギタリストを目指したというポール・コゾフ。その生涯はあまりにも短く、燃え尽きてしまった。1950年9月生まれのコゾフが、今、生きていれば55歳。でも、彼が上手にバランスを取りながら、器用にギターを弾く姿など、まったく想像できない。