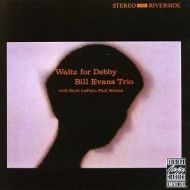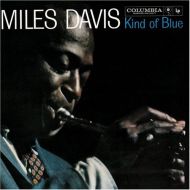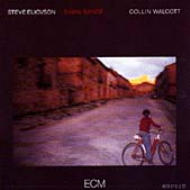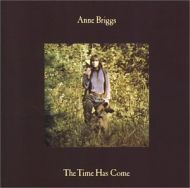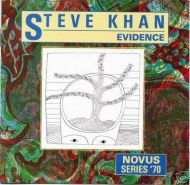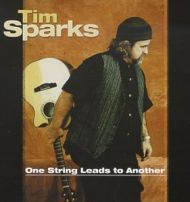●Bill Evans: Waltz for Debby
ビル・エバンスがらみのアルバムを続けて紹介したので、次は彼のリーダー作を取り上げてみよう。数え切れないほどの名作を残しているビルだが、定番中の定番が本作。1961年6月25日、ニューヨークの老舗ジャズクラブ、ヴィレッジ・バンガードでのライブ収録盤である。この日の演奏は、『Waltz for Debby』、『Sunday at the Village Vanguard』の2枚としてリリースされている。『Sunday...』の方はスコット・ラファロのオリジナル曲などを収録しているのに対して、『Waltz for Debby』はスタンダード中心の選曲となっている。
ビル・エバンスを聴くにあたり、トリオ編成ではスコット・ラファロ、ポール・モティアンによる演奏をまず押さえておきたい。スコット・ラファロがビルのピアノトリオに参加したのは1959年のことである。ビルが当時重視していたのがインタープレイと呼ばれるスタイル。従来のビバップでのアドリブに比べて、プレイヤー相互のかかわりがより強い演奏スタイルである。ビルはこの後にも、違うメンバーによる素晴らしいトリオ演奏を残しているが、最初の、そして最も成功したスコット・ラファロとポール・モティアンによるトリオ演奏をやはり最初に紹介しなければいけないだろう。
ややルバート的なビルのソロから始まり、スコットが力強いベースラインで絡み、ポールがでしゃばりすぎず、かといってしっかりと存在感のあるブラシワークで支えるというパターンも一つの特徴ともいえよう。ビルのピアノは、これまでのジャズ・ピアニストとは少し趣きが異なり、リリカル(詩的)という表現がピタリとはまるものだろう。あくまでも違いという観点からだが、黒人ピアニストに対して白人ピアニストとしてくくられる「違い」を確かに感じる。単に激しい、激しくないということではなく、感情をストレートに表出させるのではなく、強い思いを内面に押しとどめつつも、それがじわりじわりと染み出てくるような印象を受ける。
ビルにとって、重要なパートナーともいえるスコットは、この演奏のわずか10日後に交通事故で他界をしてしまう。その喪失感はとても大きく、1年近くビルは演奏活動を休止してしまう。しかし、当時の敏腕プロデューサー、クリード・テイラーの励ましを受け、さまざまな演奏フォーマットでの活動を再開する。
ビルについて書かれたテキストによると、彼はこのアルバムには気に入らない点があるといっていたそうである。ヴィレッジ・ヴァンガードは老舗ジャズクラブで、客は熱心なジャズファンが多いといわれるが、このアルバムでは、グラスの中で氷が音を立てていたり、客席の雑音が結構録音されている。ビルは、観客がこのような音を立てていることが気に入らなかったということらしい。確かに、日本のジャズ・クラブではあまり見ないような、「ゆるい」雰囲気がそれらの音から伝わってくる。少々音を立てたからといって非難されようとも、この素晴らしい演奏を目の当たりにしていた人は、ほんとに幸せであろう。