●Anne Briggs: The Time Has Come
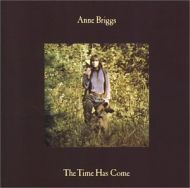
Anne Briggs (vo, g, bouzouki)
60年代から70年代にかけて活躍したブリティッシュ・フォーク(トラッド・フォーク・リヴァイヴァルと呼ばれる動き)では、女性シンガー(ヴォーカリスト)がひときわ輝いていた。以前紹介したペンタングルのジャッキー・マクシー、フェアポート・コンヴェンションのサンディ・デニー、スティーライ・スパンのマディ・ブライアーがその代表格だが、もう一人、主にソロ活動をしていたアン・ブリッグスのことを忘れることはできない。
本作の邦題が『森の妖精』とあるためなのか、アンはブリティッシュ・フォークの妖精系シンガー(そもそもイメージがよくわかないのだが・・・)と呼ばれることもあるようだが、とても意思的な歌声が印象的で、妖精というイメージはあまり当てはまらないような気がする。
イングランド中部のノッティンガムに生まれたアンは、いつしか地元のコーヒーハウスなどでトラッド・フォークソングを歌うようになるが、5-60年代のトラッド復興運動の中心的存在、イワン・マッコールやA.L. ロイドなどと出会うことで、瞬く間に表舞台に立つようになっていく。特にロイドからはトラッド・フォークの豊かな世界を伝授され、彼女のその後の音楽性に多大な影響を受けていく。
プロとしてのキャリアを踏み出す以前に、スコットランドを旅行しているときに知り合ったというバート・ヤンシュは、いうまでもなく、ペンタングルで活躍したシンガー/ギタリストであるが、バートはアンを通じて、ロイドなどが研究・伝授していたトラッド・フォークの奥深い世界を知っていくのであった。また、アンはバートからオープンチューニングなどのギター関連のテクニックや、ソングライティングを教わったとある。
バートがジミー・ペイジをはじめ、数多くのミュージシャンに影響を与えたことを考えると、そのバートに重要な橋渡しをしたアンの存在はとても大きいことがわかる。
本作では、インストも含めギターとブズーキーの演奏と歌をアンが一人でおこなっている(アルバムのクレジットには明記されていないのできちんと確認できているわけではないが)。特に、楽器の演奏は派手さはないものの、とてもしっかりしたピッキングで、女性らしからぬ力強さすら感じさせるものだ。ブリティッシュ・トラッド独特の雰囲気なのだが、幽玄でしっとりとした中にも、時折キラリと光るものを感じられるのは、なんとも不思議だ。コード進行はちゃんとあるのだが、モーダル的な浮遊感からは、不安定な気持ちの揺らぎにも似た危うさが感じられる。
アンは、本作を発表した後、音楽活動を離れてしまう。育児のためといわれているようだが、一方では、自分自身の歌声に対してコンプレックスを持っていて、レコーディングを非常に嫌っていたともいわれている。90年代に入り、過去の録音を集めてCDとしてリリースしたのをきっかけに、音楽活動を一時再開したらしいが、1,2度の演奏以外には目立った活動の話は入ってこない。


コメント
大好きなアルバムです〜。ラストの曲が特に!
僕も「歌はあまりうまくない」という評論家の文章を読んだ事があります。確かに歌唱力では、キッチリした御三家には一歩を譲る感じですが、独特の世界を作る人なので僕は同じくらい好きです。
アルバムもっと出して欲しかった反面、このくらいで良かったかも・・・・とも思います。
Posted by: 伊藤賢一 | July 7, 2006 06:59 AM
>伊藤賢一さん
いらっしゃいませ。
楽器編成もシンプルなので、他のグループと比較しても、アン自身の世界観がより強く出ていますね。
マーティン・カーシーが「彼女は自分を演出することなく、とても情熱を持ってうたっていたのに・・・」とコメントをしていたのを見ると、ミュージシャン仲間から見ても彼女に対する評価には納得がいかなかったようです。バートも「アンはもっとも過小評価されているアーティストの一人だ」といっていますね。
1990年にロイドが亡くなった後、追悼コンサートでステージに立ったようですが、決してレコーディングスタジオに向うことはなかったそうです。自分の歌を再び録音するということには、依然として強いわだかまりがあったのかもしれません。
このアルバムを聞くと、確かに若さからくるみずみずしさ、青々しさというのも感じられます。熟成された彼女の歌を聴いてみたいと思う反面、やはり一番の魅力は、若さも一因となっている不思議な「危うさ」なのではと思うと、その後、アルバムリリースをせずに良かったと思えるのも確かです。
Posted by: Ken | July 7, 2006 09:49 AM