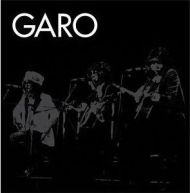●サディスティック・ミカ・バンド: 黒船
最近、木村カエラをボーカルに迎え、コマーシャルがきっかけで活動を再開したサディスティック・ミカ・バンド。以前桐島かれんをボーカルで参加させたときに比べれば、遥かにいい感じに仕上がっているが、やはりオリジナル・メンバーによるものからまず聴いてほしいものだ。
加藤和彦といえば、フォーク・クルセイダースのイメージが強かったが、イギリス志向の飛び切りポップなミカ・バンドが出てきたとき、それまでとの方向性の違いにびっくりしたものだった。メンバー一人ひとりは、スタジオミュージシャンとしても活躍していた猛者ばかり。当時の奥さんだった加藤ミカの決してうまいとはいえないがなんともいえない味のあるボーカルと相まって、強烈な存在感を放っていた。
そんなミカ・バンドがロンドンから敏腕プロデューサー、クリス・トーマスを迎えて製作したのが本作である。クリスはピンク・フロイドをはじめとするプロデュースで活躍していて、イギリスで最も有名なプロデューサーの一人といってもよかった。そんなクリスが日本という地の果てのロック・バンドのプロデュースをするというニュースに、誰しもが驚いた。イギリス、ロンドン志向の強かったことにくわえ、日本語でのロックには抵抗が強かった日本国内の市場に対する反発心もあったかもしれないが、このアルバムを製作した翌年には、イギリスを代表するバンド、ロキシー・ミュージックのロンドン公演で前座を務め、大反響でロンドンっ子たちに迎え入れられる。
当時、私はまだ中学生だったが、なんとなくこれからの音楽はロスやニューヨークだろうという雰囲気を掴み取っていたので、「何でいまさらイギリス? ロンドン??」という気持ちが強かったことをよく覚えている、もちろん、その後、ロンドンからパンク・ムーヴメントが起こることなどは、まったく想像していなかった。
まるでワイドショーネタだが、クリス・トーマスはこのアルバムのプロデュースがきっかけで、加藤ミカと不倫関係になり、その後、加藤和彦とミカは離婚し、バンドは解散となる。ミカは単身イギリスに渡り、クリスとしばらく生活を共にすることになる。今井裕、高橋幸宏、高中正義、そして小原礼にかわってベースで参加していた後藤次利の4人は、新たにサディスティックスと名前を変え、インストのバンドとしてしばらく活動をおこなっていった。
この時代、日本語のロックはノリが悪いといわれていたが、そんな声を払拭するほど完成度が高かったのが、若干年代が前後するものの、はっぴいえんどとこのミカ・バンドだったと思う。片やアメリカ的、もう片方はイギリス志向という違いも、今になってみるととても興味深い。アルバムのストーリー立ても含め、綿密に練られた音楽は、クリスの力を借りているとはいえ、やはり加藤和彦の力だろう。アルバムを通して聴くと、一つのショーを観に行ったようなイメージが残るのが面白い。
ギターの高中正義に関しては、サディスティックス~ソロの初期の演奏を一時期聴きまくっていた頃がある。高校生の頃はひたすらコピーをして、文化祭でバンド演奏をしたときにも3曲ほど取り上げるほどの入れ込みようだった。この頃のエピソードについては、いずれ高中のアルバムを取り上げるときにでも紹介してみたい。