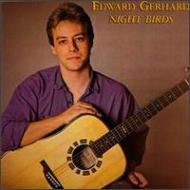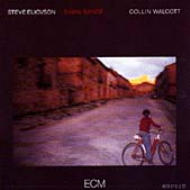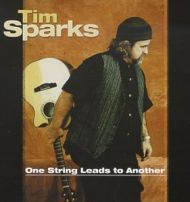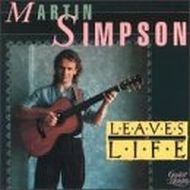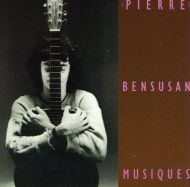●Edward Gerhard: Counting the Ways
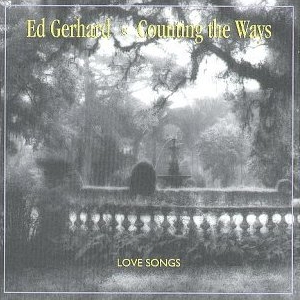
Edward Gerhard (g, lap steel, b, per)
Martin Simpson (g)
Bob Brozman (lap steel)
Arlo Guthrie (g)
Ray Brunelle (ds)
『Night Birds』で触れたが、エドに初めて会ったのが1998年春の初来日のときだった。アーヴィンが自分のギターの音のプレゼンテーションにエドのアルバムを持っていたくらいだったので、てっきりSomogyiギターを使っていると思い、とても楽しみに南青山MANDALA似足を運んだ。中川イサトさんが中心となって、エド・ガーハード、プレストン・リードを招き、小松原俊さんと4人のジョイントという実に豪華なライブだった。
それぞれが個性的で味のある演奏を繰り広げ、心待ちにしていたエドのステージが始まった。彼が手にしていたのはアーヴィンの楽器ではない!! 「えぇっ」と驚きながら見るとBreedloveのあまり見たことのないモデルだ。
MCでこの楽器が来日直前に完成して渡され、今回が初のステージお目見えとのこと。演奏自体はとてもすばらしいもので楽器の違いなどあまり気にならなくなり、気がつけばすっかり音楽を楽しんでいる自分がいた。
ライブのあとエドに話をし、近々バークリーにギター製作を勉強しに行くというと、「Ervinのところかい? 彼は本当にいい製作家だよ。いい友達だし」と笑って答えてくれた。
このアルバムがリリースされたのが1996年。実はこのときすでにエンドースメントを受けてBreedloveを使っていたのだった。BreedloveはもともとTaylor社にいたLarry BreedloveがクラフトマンのSteve Hendersonと1990年に立ち上げた比較的新しいギターメーカー。外見的には特徴的なブリッジのデザインが印象的だが、立ち上げ直後に合流したDon Kendallが開発したJLDブリッジ・システムを採用していたのが実に斬新的だった。
アメリカに渡ってアーヴィンの元でギター製作を手伝いながら勉強をする日々を送っていた頃、エドと再会する機会があった。98年の夏、ベイエリアの北部にあるSan Rafaelという街で開催されたAcoustic Guitar Festivalの会場でのことだった。「僕のことを覚えている?」と聞くと、エドは笑って「もちろん!」と答えた。ライブで使うメインギターを変えた後も、エドとアーヴィンの親交は変わることなく続いていたのである。向こうのギター展示会では、自分のギターのプレゼンテーションの時間が設けられていることが多く、主催者側が手配したギタリストか、それぞれが各自で依頼したギタリストに別会場(このときは大学が会場になっていたので展示会場とは別の教室だった)で30分ほど演奏をお客さんに聴いてもらうことが出来る。
アーヴィンはマーティン・シンプソンに演奏を依頼していたのだが、当日、マーティンの友人がアクシデントに巻き込まれて、時間まで到着できないというハプニングが発生してしまった。急遽、旧友のエドに演奏を依頼したところ快諾してくれて無事にプレゼンテーションを終えることが出来た。期せずして、エドがアーヴィンの楽器を演奏(それもピックアップを搭載していない楽器だったのでマイク収音というおまけつきだった)を聴くことが出来たが、ギターも演奏自体もすばらしく、聞きながら思わず鳥肌が立つほどだった。
さて、少しこのアルバムについて触れてみよう。副題にLove Songsとあるように、バラードものを中心にイギリスの古い伝統歌、ビートルズやミシシッピ・ジョン・ハートの楽曲、アフリカ、メキシコ、フィジーのラブソングをギター曲にアレンジしている。比較的ゆったりした曲ばかりなのだが、メロディラインの多彩さもあいまって単調な感じはまったくなく一気に聴いてしまう。ライブでの定番曲も多いのでエドの代表アルバムといってもよいが、その中でも白眉の出来はやはり「The Water is Wide」だろう。
この曲のルーツははっきりしたことはわかっていないが、17世紀ごろにイングランドもしくはスコットランドで歌われていたメロディに19世紀ごろにバラッドといわれる口承の物語を歌詞にして載せたものだといわれている。このスタイルは多少形が違っていはいるもののアメリカでも見られ、この曲をもともとアメリカの曲だと思っている人も少なくないという。
アイリッシュ、ブリティッシュのシンガーのみならず、その美しいメロディからインストとしても良く取り上げられ、特にギターソロにアレンジされているものも多い。その中でもエドのアレンジは、いつものように決して奇をてらうことなく、それでいてユニークで聴くものを引き込む力のあるものだといえる。この一曲を聴くためだけにこのアルバムを手に入れる価値は十分ある。
このアルバムではメインにブリードラブのギターを使っているが、実は「The Water is Wide」、「My Creole Belle」および「Isa Lei」のメインギター(この曲はオーバーダブでエドが複数のパートでギターを弾いている)ではSomogyiを使っていると彼はHPでアナウンスしている。
1998年の初来日以来、毎年とまではいかないが幾度となく日本に来ているエド。パートナーのケリーともども大の親日家で、日本の聴衆の前での演奏を本当に楽しんでいる様子がいつも伝わってくる。
アメリカでは毎年12月に行っているクリスマス・コンサートのプログラムでの演奏を去年から日本でも行うようになった。ことしも11月25日に東京の白寿ホールでクリスマス・プログラムでのコンサートが開催される。オリジナル曲をたくさん聴けないのは少々残念ではあるが、思いのいっぱい詰まっているクリスマス曲をエドのつむぎだすすばらしいギターサウンドで堪能できるのはとても楽しみである。