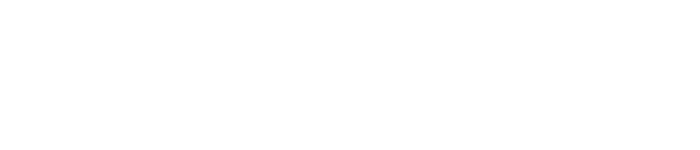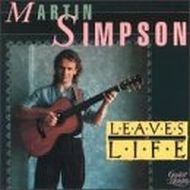John Williams (g)
クラシック・ギターを現在のような形まで引き上げた最大の功労者は、アンドレス・セゴビアである。それまでは、ギターは小さい空間でのみ演奏される楽器という認識しかなかったが、ギター製作者、作曲家たちに積極的に働きかけ、コンサートホールでの演奏に耐えうる楽器と、ギターの特性を生かしたレパートリーの拡大に、尽力したその功績は計り知れないものがある。同時に、後進の教育にも非常に熱心で、彼の元から数々の素晴らしいギタリストが誕生した。
ジョン・ウィリアムズはオーストラリア生まれ。ジャズ・ギタリストの父親の影響もあり、幼い頃からギターを弾き始める。その後、イギリスのロンドンへ移り住み、14歳の頃にロンドンのコンウェイ・ホールで演奏しているのをセゴビアに認められ、ロンドンの王立音楽院で学ぶ一方、セゴビアの元でも研鑽を積んでいった。ジョンはセゴビアの教えを受け、もっとも成功した一人として知られることになるが、世界各地を演奏してまわるにつれ、クラシックの範疇にとどまらず、さまざまなジャンルの音楽エッセンスを吸収していく。厳格に自分の教えを受け継いでいくことをよしとしていたセゴビアとの間に、何らかの考え方の相違が生まれてきたとしてもおかしくは無い。事実、ジョンは、自分の技術の中で、師事してきたセゴビアをはじめとする指導者たちから学んだものの割合は、決して大きいものではないともいっている。
クラシック・ギターへの計り知れない貢献をした一方で、セゴビアによって、長らく日の目を見ることができなかった面もある。本作は、パラグアイの作曲家アウグスティン・バリオスの作品集で、最近では『大聖堂』などは、クラシックのレパートリーとしてもポピュラーになってきている。しかし、セゴビアはバリオスの曲を「演奏するに足らぬつまらぬもの。彼の曲を演奏するくらいなら、他に弾くべき曲は山ほどある」と酷評していた。セゴビアがクラシック・ギター界の中心で力を振るっていた時代には、バリオスの曲を演奏するプレイヤーは数えるほどだったという。
リリカルで、哀愁を帯びたバリオスのメロディ・ラインは、ナイロン弦の音色と相まって際立った美しさを見せる。ジョンの非常にシャープで輪郭のたった演奏は、バリオスの曲を演奏している録音の中でも、トップクラスの仕上がりだと思う。彼が愛用しているのは、オーストラリアのグレッグ・スモールマンという製作家のギター。通常のクラシック・ギターと比べて、表面版の補強の仕方がまったく異なるスモールマン・ギターは音の立ち上がり方が独特で、ジョンの演奏スタイルを特徴付ける要素として、今や欠かせぬものとなっている。
ジョンは80年代には、ポピュラー音楽演奏にもかなり力を入れ、自らSKYというグループを結成する。こちらでは、ピックアップを内蔵したオヴェイションのナイロン弦モデルを使い、バンド編成での演奏をおこなっていた。この頃、クラシック・ギターの演奏をほとんど耳にしていなかった私だが、「クラシック・ギター界の貴公子がフュージョン音楽を演奏する!」といったようなキャッチコピーで宣伝していたことは覚えている。ただ、クラシックのファンからは、この時代については「非常に無駄な回り道をした」という厳しい声が多い。
ジョンの演奏するナイロン弦ギターの音をポピュラーなものにしたのは、マイケル・チミノ監督の『ディアハンター』のメインテーマとして使われた、「カヴァティーナ」の演奏だろう。ナイロン弦ギターを手に入れたら、この曲を練習して弾けるようになりたいと思いながら、ずいぶんと長いことたってしまったが・・・。