
James Taylor (vo, g, p)
Russ Kunkel (ds, per)
Leland Sklar (b)
Carole King (p, chorus)
Danny Kootch (g, per)
Peter Asher (produce, per, chorus)
Joni Mitchell (chorus)
Kevin Kelly (accordian, p)
John Hartfor (banjo)
Richard Greene (fiddle)
Kate Taylor (chorus)
ジェイムス・テイラーの音楽に最初に接したのは中学生のときだった。CSN&Yの紹介でも触れたが、中学のときに通っていたギター教室で取り上げたのがきっかけである。スリーフィンガー奏法を徐々にマスターしてきたこともあり、「これで大抵のフォーク曲は弾けるだろう」と思い上がっていたころでもあった。
教室で習う順番からすると、スリーフィンガーはアルペジオ奏法よりも若干高度なテクニックと感じていたため、ジェイムスの譜面をもらったときに最初に思ったのは、「なんだぁ、アルペジオかぁ」ということだった。
ところがどうしてどうして、弾いてみると単純なアルペジオではなく、なかなか上手くできない。それまでの定型パターンのものとは違い、メロディやコード進行に併せて、実に効果的なオカズが入っているのだ。彼の曲を何曲か練習していくにしたがい、入れているオカズのフレーズは比較的手癖のようなものだと気付くのだが、それはずいぶん後になってからだった。
歌伴のギターとしては、今なお最高峰の演奏だと信じてやまない。歌とよく絡みつつでしゃばりすぎつ、かといってちゃんと存在感もある、こんなギターを弾くことができる人は滅多にいないだろう。
カントリー的な要素とジャジーな雰囲気とブルースの香りも感じるギタープレイは、今聴いてもとても新鮮だ。
当時、愛用していたのはギブソンのJ-50というモデル。ギブソンのアコースティック・ギターはかなり個体差が大きいこともあるが、私自身、何本か試奏したことはあるものの、ジェイムスのような音のものには一度たりとも出会ったことがない。あの独特の音は、ギターそのものというよりも彼のプレイによるところが大きいような気がする。
東海岸ボストン生まれのジェイムスは、1968年に最初のソロ名義のアルバムを、ビートルズのアップルレコードレーベルからリリースする。専門家の間では注目されたものの、商業的にはまったく振るわず、失意のままプロデューサーのピーター・アッシャー(本アルバムでもプロデュースをしている)とともにアメリカに戻り、カリフォルニアに拠点を置いて活動をおこなっていく。
1970年にリリースした2作目『Sweet Baby James』(これはいずれ別途紹介したい)で成功を収め、瞬く間にシンガーソングライターとしての地位を確立する。メッセージ性の強いプロテスト・ソングを歌っていたピート・シーガーやボブ・ディランなどとは一線を画し、日常的なことや恋愛などを繊細に歌い上げるシンガーソングライターは?というと、真っ先にあがるのがジェイムスだろう。
本作は1971年に発表した第3作。楽曲の構成、バリエーションともに素晴らしく、大変聴き応えがある。ギターや歌、コーラスなどを分析していくと、勉強になる点も多いが、そんなことを意識せず、音楽にどっぷりと浸かるのが最高の楽しみ方だろう。
初期から最新のものまで、音楽のスタイルにいろいろと変化はあるものの、駄作がなくどれをとっても素晴らしいものとなっている。初めて聴いても、なんとなくなつかしい香りがし、それでいて飽きさせないものがある。これこそがジェイムスのマジックなのかもしれない。
現在も変わらぬ歌声で、ライブも含めた活動を積極的におこなっている。日本のギタリストやシンガーソングライターが、彼の影響を強く受けたと語っているのが多いのもうなづける。
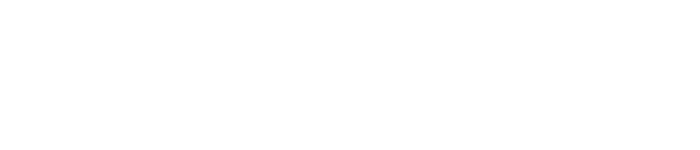

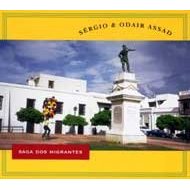
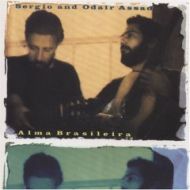 アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の
アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の



