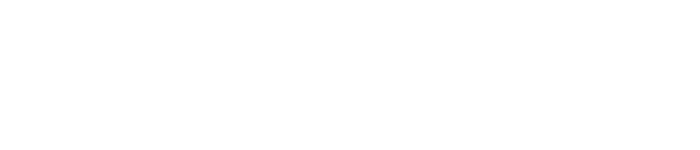Alex de Grassi (g)
スティール弦ギターでのインストゥルメンタル演奏をポピュラーにしたことに貢献したレーベルとしてWindham Hillをあげることに異論を唱える人は少ないだろう。1970年代半ばに、スタンフォード大学のあるパロ・アルトでWilliam Ackermanが立ち上げたレーベルは、ピアノのジョージ・ウィンストンを初めとする、アメリカのフォークの伝統を持ちつつ、ジャズやクラシックの要素を取り入れた良質な音楽を演奏する仲間たちの活動を、世の中に伝えていこうとすることがベースとなっていた。
アレックス・デ・グラッシは同じベイエリアにある公立校の雄、カリフォルニア大学バークリー校(ちなみにスタンフォードは西海岸を代表する私学)で地理経済学を専攻していたが、卒業を間近に控えた時期、いとこのウィリアム・アッカーマンが立ち上げたウインダムヒル・レーベルからギター演奏による作品『Turning: Turning Back』をリリース。この作品が好評だったこともあり、彼はギタリストとして一本立ちしていくことになる。
アメリカを代表するギター製作家、Ervin Somogyi(日本ではアーヴィン・ソモギと呼ばれているが、英語ではソモジという音の方が近い。但し、Ervinによれば、彼の母国であるハンガリーではショモジと発音するので、どちらにせよもともとの発音とは違うということだ)は、70年代後半からギター製作に本格的に打ち込み始めるが、スティール弦の個人製作家というのは、それまでに前例がほとんどなく、苦戦を強いられていた。
そんな折、同じベイエリアでの新興音楽勢力ともいえるウィンダムヒル・レーベルが立ち上がり、ウィリアム・アッカーマンがアーヴィンのギターを使い始めるようになる。ウィンダムヒルのギタリストたちは、ウィリアムから「今までに無い、素晴らしい音のギターがある」と、アーヴィンのギターを紹介され、次々とレコーディングに使うようになっていった。
アーヴィンにとっては、早い段階で、自分のギターを愛用してくれたアレックス・デ・グラッシとダニエル・ヘクト(彼は『Willow』というアルバム一枚だけを同レーベルからリリースしている。現在はギター演奏をおこなっておらず、作家として活動しているらしい)は、特に思い入れがあるようで、工房には80年代前半に二人がおこなったコンサートのポスターを飾っていた。もちろん、二人ともアーヴィンのギターを手にして写真に写っている。
本作は、アレックスにとっては4枚目のアルバム。初期の作品に比べると、演奏スタイルも熟成されてきている。楽曲の構成はクラシックの雰囲気もあり、ヨーロッパ的な香りがするのも面白い。空間系のエフェクト(おそらくコーラスかハーモナイザーの類と思うが詳細は不明)を効果的に使っているので、音のバリエーションも楽しめる。ただ、ギターを作る側から言えば、生音の素晴らしいアーヴィンの楽器を使っているだけに、加工をしない音をもっと聞かせて欲しかったのは正直な気持ちだ。
 残念なことに、本作は現在入手困難になっているようである。手に入りやすいものとしては、Windham Hillレーベルでのベストアルバム『A Windham Hill Retrospective』を変わりにあげておく。『Southern Exposure』を含む過去4作とウィンダムヒル・アーティストのライブ盤からの選曲で、アレックスのウィンダムヒルでの演奏を知るには最適であろう。
残念なことに、本作は現在入手困難になっているようである。手に入りやすいものとしては、Windham Hillレーベルでのベストアルバム『A Windham Hill Retrospective』を変わりにあげておく。『Southern Exposure』を含む過去4作とウィンダムヒル・アーティストのライブ盤からの選曲で、アレックスのウィンダムヒルでの演奏を知るには最適であろう。
いい作品が、コンスタントに入手できるような状況をぜひとも作ってもらいたいものだ。
アレックスは現在もベイエリアをベースとして演奏活動をおこなっている。新しい作品もなかなか評判がいいようなので、機会を見て聴かなければと思っている。