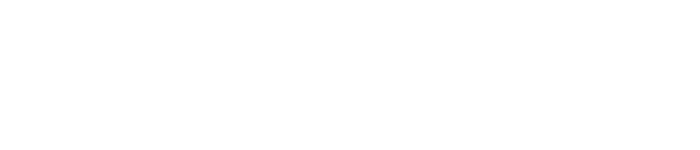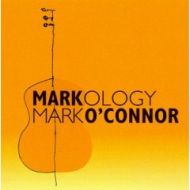井上 陽水 (vo, g)
星 勝 (arr, g,)
安田 裕美 (g)
矢島 賢 (g)
竹部 秀明 (b)
高中 正義 (b)
稲葉 国光 (b)
田中 清司 (ds)
深町 純 (arr, p, key)
本田 竹廣 (p)
飯吉 馨 (p)
ギターの入った音楽に没頭するようになったのは、井上陽水のアルバムを聞いてからだった。それ以前に、ギターに関心を持ったことはあったっけと、思い起こしてみると、小学校中学年の頃にさかのぼる。母親がある日、突然(のように私には思えた)ギターを買ってきたのである。たしかFujiというブランドのクラシックギターだった。

それと、多少前後したかもしれないが、一枚のレコードが我が家にやってきた。森進一の『影を慕いて』。古賀メロディーを若き森進一が歌い上げているものである。つまり、演歌のギターが、一番最初に原体験として刷り込まれたのだった。それでは、家にあったギターで演歌ギターの練習を始めたかというと、そうではなかった。とりあえず、手元にあったクラシックの教則本を見ながらポロポロと練習曲等を弾き始めただけだった。
陽水の曲を初めて聴いたのもラジオからだった。『傘がない』というタイトルの曲は、まだ、学生運動や政治活動が盛んな時代に、彼女のところに行くのに傘がなくて困っているという内容の歌詞だった。当時は、社会問題について、関心がないこと自体が罪だと糾弾するような時代。その中にあって、社会で起こっていることよりも自分が傘を持っていないということを淡々と歌っていることが、あまりに衝撃的だった。
一か月分のお小遣いを握り締め、レコード屋でシングル盤を買って、何度も何度も聞き返した。知り合いが、陽水のLPを持っているというので、借りてきてカセットに録音し、テープが伸びてしまうまで聴き続けた。当時、フォークのスターといえばまずあがったのがよしだたくろう。しかし、シンプルなコード進行に、直情的な歌詞をのせて、時には攻撃的に歌うたくろうは、がさつな感じがしてどうしても好きになれなかった。それに対し、陽水は、繊細で弱々しくはあったが、ディミニッシュコードなども用いたおしゃれなコード展開で、ギターのアレンジも秀逸、心の弱い部分を歌う独特の世界観に強い共感を覚えた。楽譜集を買ってきて、載っている曲を片っ端から練習したことは言うまでもない。
このアルバムは、陽水名義でリリースした2作目。歌を邪魔せず、かといってきちんと存在感のあるギターのアレンジが実にすばらしい。陽水の歌声は、現在に比べるとはるかに繊細で、その歌詞から伝わってくる、今にも壊れてしまいそうな世界とぴったり合っている。陽水はある時期以降、カミングアウトをして、自ら屈折した部分を堂々と出すようになったが、この当時は、屈折したところを、自分でも疑問を感じながら、気持ちに正直に表現せずにはいられないという雰囲気が伝わってくる。歌詞は時として不条理なまでもの情景を述べる。『東へ西へ』での、”・・・電車は今日もすし詰め、(中略) 床に倒れた老婆が笑う・・・・”といった内容も、さらりと歌いながら、歌われているものはすさまじいばかりだ。当時は考えも及ばなかったが、今、改めてこの歌詞を読むと、まるでつげ義春のマンガにでも出てきそうな不条理の世界がイメージされるのは私だけだろうか。
この頃のアルバムは、参加ミュージシャンのクレジットを見るのも楽しみのひとつ。星勝は元モップス(鈴木ヒロミツがボーカルをしていたグループ)で、陽水の初期からアレンジ全般を手がけている。その関係は現在でも続いているから、30年以上の長い関係というわけだ。リリースされたのが1972年だということを考えると、高中正義は成毛滋(当時は、グレコのギターを買うと、成毛滋のロックギター教則カセットか、竹田和夫のブルースギター教則カセットがついていたのが懐かしい)率いるフライド・エッグにベーシストとして参加していた時代なので、ギターではなくベースで参加しているのもおかしくない。深町純はその後、オールスターズというグループを率いて『オン・ザ・ムーブ』という名曲をヒットさせるし、本田竹廣(残念なことに、つい最近亡くなられた)は、フュージョンブームの中で、日本の旗頭となるべくネイティブ・サンを結成して一世を風靡する。
これだけの実力派が脇を固めているので、やたら音を重ねているのではないのに、必要な音が必要な空間を満たしている。シンプルなスタイルの音楽が、ストレートに心に響く。