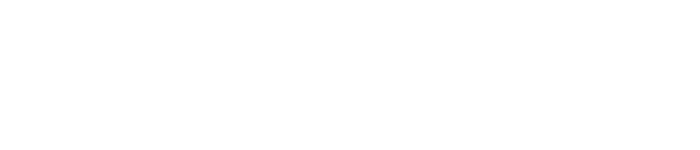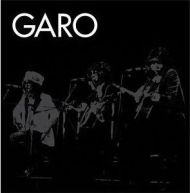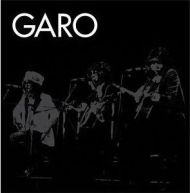
堀内護 (vo, g)
日高富明 (vo, g)
大野 真澄 (vo, g)
他
ガロの歌を最初に聴いたのは、おそらく『学生街の喫茶店』の大ヒットのときだったと思う。その後も、数々のヒットを飛ばしたのであるが、ギターとコーラスが若干印象には残るものの、当時は数多くあったポップス色が強いフォーク系のグループという程度の認識しかなかった。ただ、マーティンの最上位機種のD-45(1970年ごろの定価が75万円くらいだったようである)を持っていたので、貧乏なイメージの強かったフォークシンガーと比べて、ずいぶんとお金を持っているんだなぁと思ったことを覚えている。
お小遣いの少ない小学生にとって、ガロのメジャーなヒット曲は、わざわざレコードを買いたいと思うほどではなかった。最初に彼らの曲を耳にしていらずいぶんたった後のことだが、ラジオから聞こえてくる『一本の煙草』という曲が、とてもおしゃれで気になった。当時は東京の大井町に住んでいたのだが、、同級生の実家でもあったアップルレコードという行きつけのレコード店に、シングル盤を探しに行ったのは、その直後のことだった。
お目当てのシングル盤はすぐに見つかり、白黒の渋いジャケットに惹かれつつも、「他に何かいいものがあるかもしれない」と思い、フォーク系のアーティストのシングルを物色してみることにした。そこで、もう一つ気になっていたアリスの『紫陽花』というシングルを見つけてしまった。どちらを買おうか、かなり長い時間迷った末、なんと手にしたのは、アリスのシングル。いまや演歌歌手となってしまったベーヤンこと堀内孝雄がメインボーカルの曲である。今思い起こしても、かなり演歌色の強い曲といってもよいものだった。
そんなわけで、ガロのレコードを手にする機会を自ら逃してしまった。その後はロック~フュージョン~ジャズへと走っていく少年にとって、ポップス色(それもたぶんに歌謡曲的な要素が含まれていた)の強いフォークはもはやおしゃれなものとは映らず、長いこと思い出すこともない存在となっていた。

大人になってかなりしてから、ガロがよく聴いていたCSN&Yのコピーバンドから始まったことを知り、俄然興味がわいてきた。
すでに、彼らのCDは入手困難で、唯一手に入ったのがシングルリリースを中心にしたヒット曲集のアルバムのみ。ギターとコーラスには確かにCSY&Y的な雰囲気は感じられるものの、グイグイ著ひきつけられるほどの魅力は感じられない。
いろいろと調べていくと、ファーストアルバムが一番CSN&Yの影響が濃い演奏となっていること、所属事務所(もしくはレコード会社)の意向で、ヒットを狙った路線を強いられ、なかなか自分たちのやりたかった音楽ができなかったことなどがわかってきた。そこで、ファーストアルバムを入手しようとしたところ、すでに廃盤。時折オークションで見かけても、1万円近くの値段で取引されているような状態だった。
そうこうしているうちに、オリジナルアルバム8枚と未発表曲、テイク、ライブなどを収録したCD2枚とDVD1枚を組み合わせた本ボックスセットがリリースされるという情報を掴んだ。確かにセットとなると値段は高いものの、プレミアがついているものを買うことを考えたら、はるかにお得。おまけに、未発表曲にはCSN&Yのカバー演奏も含まれているというから、これは買わないわけにはいかない。
完全予約生産というこのボックスセットは当初2006年8月にリリースされる予定だったが、DVDに収録しようとしていたCSN&Yの曲の使用承諾を得るのが難航し、発売は延期。結局、映像収録分は許可が下りず(ライブでのカバー演奏は収録されている)に内容を若干変更して11月末にリリースと相成った。すでにamazonでは在庫切れとなっているので、これから注文をしても入手できるかどうかはわからない。
発売順にCD全10枚を続けて聞くと、事務所側がやらせたかったことと自分たちが本当にやりたかったこととの狭間でメンバーが苦しみながら音楽制作をしていたことが痛いほど伝わってくる。時折顔を出す、変則チューニングを多用したアコースティック・ギターの音と3声のコーラスは、確かにCSN&Yの影響がひしひしと現れている。当時ヒットしていた曲ではなくこれらの曲を聴いていれば、どっぷりとガロの音楽に浸っていたかもしれないほどだ。
解散ライブの様子も一部収録されているが、解散の挨拶をメンバーがした後に「最後の曲です」といって演奏するのがTeach Your Children。そしておそらく続けて演奏されたのであろうFind the Cost of Freedom。Find~はCSN&Yがライブの最後にアコースティック・ギターだけを持って演奏する曲。途中から伴奏が一切なくなり、アカペラコーラスだけになる。グループの解散の最後にこの曲を持ってくることに、彼らの置かれていた状況の複雑さを垣間見たような気がした。
残念なことに、トミーこと日高富明氏は1986年に36歳の若さで自ら命を絶つ。ガロとしての生演奏を耳にすることは二度とできないのである。高かった音楽性と、市場に翻弄されたグループとしての運と不運。音楽は、やはりアーティスト自身が内から湧き上がる思いとともに作り上げていくものだと感じずにはいられない。