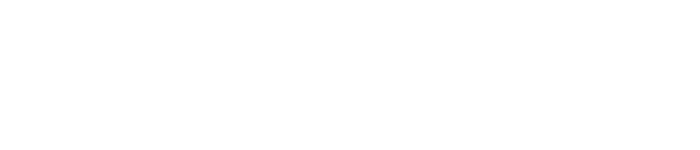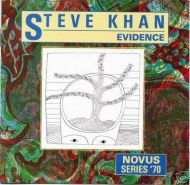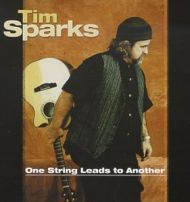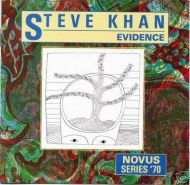
Steve Khan (g)
70~80年代初頭のフュージョン・シーンを語る上で、はずせないのがアリスタ・レコードのノーヴァス(novus)・レーベルである。アリスタは、以前紹介したラリー・コリエルの『Tributaries』をはじめ、ブレッカー・ブラザースや、STEPS(のちにSTEPS AHEADとユニット名を変更)などで活躍をすることになるマイク・マイニエリなど、重要なプレイヤーが数多くの作品をリリースしていたことで知られる。
70年代からニューヨークを拠点に、数々のセッションをこなし、実力派ミュージシャンとして評判が高かったスティーヴ・カーンは1975年から76年にかけてラリー・コリエルとギター・デュオのライブ・ツアーをおこなう。ここで、ウェイン・ショーターやチック・コリアなどの曲をギター2本で即興的な要素を交えながら、白熱のセッションを繰り広げた。このユニットでは1976年録音の『Two For the Road』という名盤を残しているが、これはまた機会を改めて紹介したい。
コリエルとのツアーを終え、スティーブはエレクトリック主体のリーダー作を3枚ほど発表するが、81年にリリースした本作では、アコースティック・ギターを前面に出しながら、コリエルとのデュオとは別軸の素晴らしい演奏を披露する。場合によっては、複数のアコースティック・ギターのみならず、エレクトリック・ギターも重ねた多重録音による演奏だが、メロディの美しさを追求したスティーヴのギタープレイ自体は、決して奇をてらったものではなくオーソドックスともいえるものなのだが、非常に緻密に作り上げられた楽曲は、これまでにない独自性の強いものである。
個人的には、少し空間系のエフェクト処理が強いのが気になるが、ギター自体の音も素晴らしい。このとき、スティーヴが弾いていたのは、デヴィッド・ラッセル・ヤングが製作したギター。デヴィッドは60年代終わりから80年代初めにかけてアメリカ西海岸でギター製作をしていた伝説の人物である。その後、ギター製作からはなれ、ヴァイオリンの弓製作家として現在も活動している。たまたま縁があって、『アコースティック・ギター・マガジンVol.18』(リットーミュージック 2003年10月刊)の「幻と呼ばれたドレッドノート」という企画で、もう一人の伝説的なギター製作家、マーク・ホワイトブックとともに取り上げたとき、二人の製作家とそれぞれのギターについて記事を書く機会を得た。デヴィッドとはメールで連絡を取り、短いバイオグラフィーながら、事実を確認しながら執筆できた。
ギター製作をする人の間では、デヴィッドは『The Steel Guitar Construction & Repair』(残念ながら、絶版になってしまっていて入手は難しいようである)という教科書を執筆したことでも良く知られている。スティール弦ギターの製作方法について書かれた最初の本であるが、今はギター製作を離れている伝説の人物とコンタクトが取れたことで、とても興奮したことを今でもよく覚えている。
メロディを歌わせるためにスティーヴが選んだのは、ウェイン・ショーターやホレス・シルバー、セロニアス・モンクなどの楽曲。その中でも、モンクの曲を9つメドレーにしてトータル18分強に渡って繰り広げらるるラストの曲は、名演というより他にない素晴らしいものだ。
残念なことに、このアルバムは現在入手が難しいようである。ただ、ネット上のmp3形式で楽曲を扱うサイトなどからダウンロードはできるようである。「Steve Khan Evidence」といったキーワードで検索すると見つかるだろう。但し、mp3は圧縮形式なので、オリジナルの音を再現できるわけではないことを認識しておく必要があるだろう。個人的には、mp3ではかなり音の密度が変わるという印象がある。
ちなみに画像のジャケット写真は「Novus series '70」というシリーズ企画でリリースされたCDのもの。LPでリリースされたのは、中央の白い部分のデザインによるものだった。